データが足りない部分を機械学習で補う
ドーナツ型のブラックホール画像、機械学習でさらに鮮明に
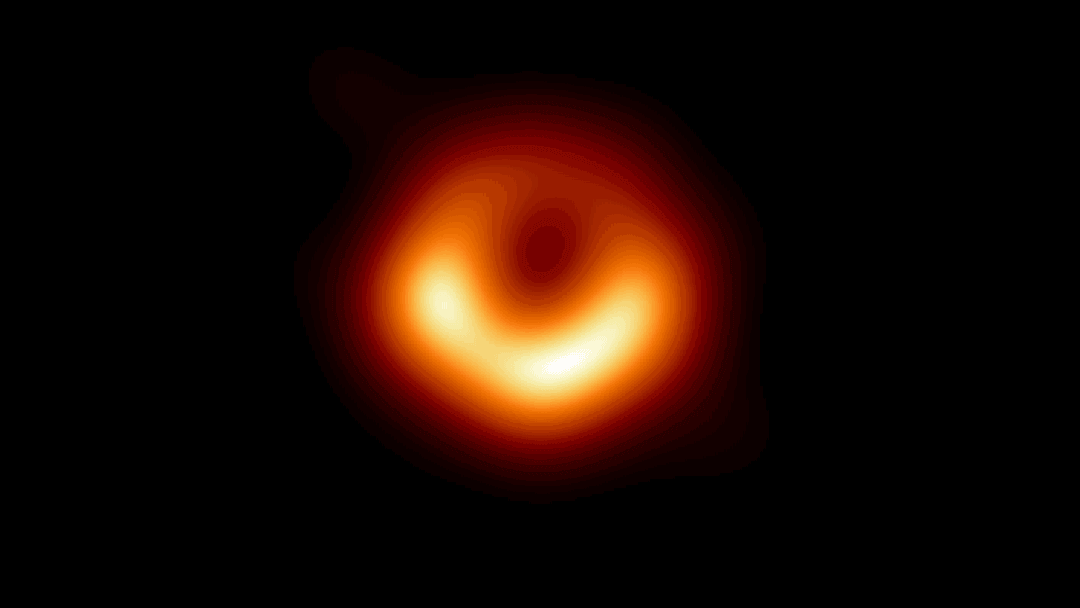
2019年に発表された、史上初めて捉えられたブラックホールの画像は、暗い宇宙の闇の中にぼんやりと赤いドーナツのようなリングが浮かんでいるように見えた。
もちろん、光でさえも飲み込むとされるブラックホールは光学的に直接見ることができない。そのため赤いリングは、ブラックホールに取り込まれた天体から放出された、高温のガスや塵などの姿と考えられる。
今回、The Astrophysical Journal Lettersに掲載された新しいレポートによると、研究者らは機械学習アルゴリズムを用いてこの画像をアップグレードした。その結果、地球から約5500万光年も離れたM87銀河の中心にある超大質量ブラックホールの姿は、当初のものよりも赤いリング部分が引き締まり、対照的に中心部分の暗闇部分がより大きく見えるようになった。
光すら飲み込んでしまうほど強い重力を持ち、目に見えない天体の存在は、18世紀ごろから想定されていた。そして、現在では天文学者でなくとも、巨大な恒星が自らの質量によって崩壊した結果、ブラックホールになるということを知っている。ブラックホールの本体は見えないが、周囲の天体を引きずり込む際に破壊された天体の欠片や塵、ガスが高温になり、ブラックホールの周りに降着円盤と呼ばれる光輪を形成する。その光を、Event Horizon Telescope(EHT)プロジェクトが捉えて画像化した。
EHTは、地球上の各地にある複数の電波望遠鏡をネットワークで接続し、ひとつの巨大な(地球サイズの)電波望遠鏡に見立てて扱うプロジェクトだ。ただ、EHTで取得されたブラックホールのデータは、互いに離れた場所にある電波望遠鏡のデータを突き合わせたものであるため、部分部分にデータの粗密があり、できあがった画像は全体にぼんやりしたものだった。
研究者らはこのデータに、PRIMOと呼ばれる手法を適用した。PRIMOとはPrincipal-component interferometric modelingの略語で、直訳すれば”主成分干渉モデリング”となる。そして、3万以上のブラックホールの生成シミュレーションで強化学習したPRIMOのアルゴリズムを適用することで、ブラックホール画像におけるデータの足りない部分を補ったとのこと。デジタル画像でいうところのアップスケーリング処理を施したと考えればわかりやすいだろう。
これにより、当初のぼんやりした画像に対して、ブラックホールがどのようなものかという物理的法則やその他の知見をデータとして適用することで、より正確と考えられる画像が得られた。
プリンストン高等研究所の天体物理学者で、元のM87の画像生成にも携わったLia Medeiros氏は、今回発表した画像について「私たちは常に改良を重ね、より良い画像を作ろうと努力している」と述べている。そして「われわれがやっていることは、画像の様々な部分の相関関係を知ることだ」と述べ「画像の上では、任意の画素に近い画素は完全に無関係ではない。(デジタル画像の)ピクセルとピクセルは完全に独立しているわけではない」と説明している。
- Source: The Astrophysical Journal Letters
- via: NPR Engadget
